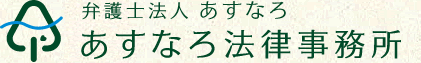1.相続人の範囲
1-1
- 私の長男は、常々親に暴力をふるったり、暴言を吐く等の行状があらたまりません。親不孝な息子には財産を相続させたくありませんが、良い方法はないでしょうか。
- 子には遺留分権利者[*]として一定の相続分が保障されています。しかし、家庭裁判所に「相続人の廃除」の申立てをすれば、子から相続人の地位をとりあげることができます。
子を廃除できるのは、子に虐待、侮辱、非行といった事情があるときに限ります(民法892条)。廃除できる場合にあたるかどうかは、弁護士にご相談ください。
2.相続財産
2-1
3.遺産分割
3-1
3-2
4.遺言
4-1
- 遺言をするには、どの程度の能力が必要ですか。
- 遺言という行為を判断できるだけの能力があれば、単独で遺言ができます。これを「遺言能力」といいます。これは、契約などの法律行為を有効に行なうことのできる「行為能力」とは別の概念です。
従って、行為能力が制限されている被保佐人や被補助人も単独で遺言が可能です(民法962条)し、未成年者でも、満15歳以上であれば遺言能力が認められます(民法961条)。また、成年被後見人も、事理を弁別する能力が一時回復した時に、2人以上の医師の立会いを得て、単独で遺言ができます(民法973条)。
ただし、いずれの場合でも、遺言をする時に、有効な意思表示をする能力(これを「意思能力」といいます。)を欠いていた場合には、遺言は無効になりますので、注意が必要です。
遺言当時に遺言能力があったかどうかでトラブルになるケースは多いので、遺言の効力に疑問がある場合には、弁護士にご相談ください。
4-2
- 遺言執行者とは何をする人ですか。
- 遺言の内容を実現するための手続を行う人で、遺言の中で指定することができます(民法1006条)。相続人が多数いるときや、第三者に財産を遺贈[*]する場合など、相続人の協力を得ることが困難であると予想される場合には、遺言の執行の円滑化のため、あらかじめ遺言執行者を指定しておくのが望ましいでしょう。遺言執行者に弁護士が成ることも可能です。
4-3
- 遺言書に、「財産の一部を環境保護団体に寄付する」との記載したい場合。遺言執行者をつけなければならないでしょうか。
- 環境保護団体への寄付も含めて遺言どおりの相続をスムーズに実現できそうなら遺言執行人をつける必要はありません。しかし、このような場合、必ずしも相続人の協力が得られるとは限りませんので、遺言執行者を設けて執行させた方がよいでしょう。
4-4
- 手が不自由で思うように遺言書が書けません。他の人に手伝ってもらったり、パソコンを使ってもよいでしょうか。
- 自筆証書遺言は、自分で書くのが原則です(民法968条1項)。パソコンやワープロを使って遺言書を作ることはできません。他人の補助については、全く許されないものではありませんが、他人によって、遺言者の真意と異なる遺言書が作成されたと疑われるようなやり方をした場合には、遺言が無効と判断されるかもしれません。トラブル回避のためにも、公正証書遺言にするのが無難でしょう。
4-5
- 夫婦共同で遺言をしたいと考えていますが、一つの遺言書に夫婦連名で遺言できるでしょうか。
- このような遺言を共同遺言といいますが、法律上、2人以上の者が同一の証書ですることはできないとされています(民法975条)。共同遺言が禁止されるのは、もしこれを許せば、遺言者それぞれが自由に遺言を撤回できなくなるからです。
4-6
4-7
4-8
- 父親が、以前書いてあった遺言書を破棄して、新しい遺言書を作りました。前の遺言書には、「この遺言は今後絶対に変更しない」と書いてありましたが、それでも遺言は変更できるのでしょうか。
- 変更できます。遺言者はいつでも遺言を撤回することができ、この撤回権は放棄できません(民法1022、1026条)。遺言者の最終意思を尊重するのが遺言の目的ですので、時の経過と共に変化する遺言者の意思にあわせて作りかえることが認められています。
4-9
- 父親が、遺言書を変更して、新たに遺言書を書き直しましたが、「やっぱり遺言を変えるのはやめた」と言って、書き直した遺言状を破り捨てました。この場合、前の遺言は効力があるのでしょうか。
- 撤回行為が撤回されたり、効力を失っても、いったん撤回した遺言は復活しないのが原則です(民法1025条)。ただし、詐欺または強迫により撤回行使が取り消されたときは、撤回された遺言が復活します(同条但書)。また、当初の遺言の復活を希望する被相続人[*]の意思が明らかな場合に、例外的に復活が認められたケースもあります(最判平9.11.13.)。
5.遺留分
5-1
- 妻子がありますが、私の死後は長男ひとりに全財産を相続させたいと思っています。どのような準備をしておけばよいでしょうか。
- 生前に、あらかじめ相続権を放棄する契約を結ぶことは、法律上認められていません。そこで、1人の相続人に財産全部を贈与又は遺贈[*]する旨の遺言をしたうえで、他の相続人に遺留分を放棄してもらうとよいでしょう(民法1043条)。生前に遺留分を放棄するには、放棄をする者が、家庭裁判所に申立てを行い、遺留分放棄の許可を受ける必要があります。